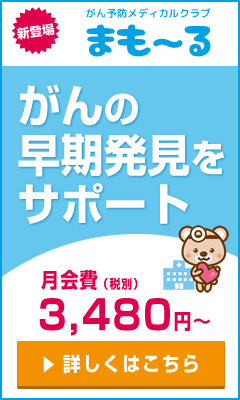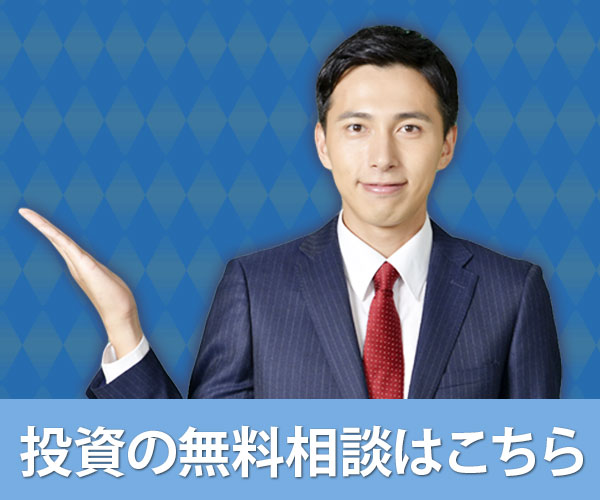- 2018-1-4
- 生命保険

生命保険に加入している人は、全体の約7割と言われていますが保険契約者と、受取人が本人だった場合死亡時の保険金受取りはどのような扱いになるのでしょうか?
また、保険金受取時にもっとも節税になる保険契約についても知っておきましょう。
【保険契約者本人が受取人になっている場合】
保険契約者本人が、受取人になっている場合保険金は一旦、契約者本人の物になります。死亡保険金は、死亡後に発生するため相続財産となります。
このような場合、保険金を相続する人のうち誰が、どれくらい受け取るのかを遺産分割協議で決める事になります。
死亡した人が、遺言書などを作成し相続する人を指定していない限り、保険金は通常法定相続人によって遺産相続がされます。
【生命保険受取人は誰にすべき?】
死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって受取時にかかる税金も変わってきます。
保険金の受取人は誰にすれば最も税金が少なくて済むのでしょうか?保険金受取時の税金を最も少なくするためには、契約者と被保険者が同一で、受取人を妻や子供にしておきましょう。
この場合、受取時に発生する税金は相続税になり最も節税ができます。なぜなら相続税の場合は、500万円×法定相続人の数が非課税金額になるからです。
法定相続人には、相続順位というものがあり、それに応じて相続する割合が定められます。税金を少しでも節税するためには、相続税になる契約パターンにしておくことを覚えておきましょう。
【生命保険の受取人変更】
生命保険契約を結婚や、就職などで見直しをする場合もあるでしょう。特に生命保険においては、受取人の変更は重要な役割をもっています。
結婚や、離婚、死亡など人生のさまざまな節目において、受取人の変更が必要になります。受取人の変更は保険会社に連絡をすれば、いつでもできます。
死亡後に相続などでトラブルが発生しないためにも、死亡時に誰にお金を残したいのかを考え受取人を決めることが大切でしょう。
ただし、保険金受取人は誰でもなれるわけではありません。基本は配偶者または、二親等以内の血族となります。
【まとめ】
受取人と、契約者が同一の場合は、相続財産とみなされます。死亡後に遺産相続でトラブルが発生しないためにも、専門家に相談をして誰がどれくらい受け取るのかを決めておくと安心です。
また、生命保険を活用して相続税対策などを行うことも大変有効ですので、ぜひ検討してみるとよいでしょう。